花火よりも難題 ── 大量の動く人間をどうやって数えるのか?
お祭り、パレード、花火大会、そしてデモ行進──
街中で行われるこうした大規模イベントでは、毎年のように「今年は○○万人が訪れました」と報じられます。
その数字を目にするたびに、つい「へえ、そんなに?」と驚かされますが、ふと、こんな疑問が頭をよぎりませんか。
── でも、それって、どうやって数えてるの?
たとえば、隅田川花火大会。
これまで「来場者100万人」と言われることが多かったこのイベントも、
2025年の公式発表では93万人とされています。
もちろん、そのスケールには圧倒されます。
でも同時に、あの雑踏のなかで、いったい誰がどうやってそんな人数を把握しているのか、不思議に思いませんか?
人は移動します。立ち止まったり、途中で帰ったり、屋台の裏からこっそり見たりもします。
数えるにはあまりにも不規則で、あまりにも自由。
そんな空間で、93万人という数字がどう導き出されているのか。
実はそのカウント方法、驚くほどアナログで、驚くほど人間くさいのです。
この記事では、隅田川花火大会を例にとりながら、街頭イベントの“来場者数”がどうやって割り出されているのか、その舞台裏をひもといていきます。
誰がどうやって数えるのか
観客としてカウントされるのは、交通規制が敷かれたエリア内にいた人たちです。
この区域が、いわば「花火大会の来場者」として公式に認定される範囲ということになります。
つまり、エリア外の飲食店やマンションの窓から見物していた人たちは ── たとえどんなに盛り上がっていたとしても ── 残念ながらその対象には含まれません。

このエリア内に、墨田区だけで23か所の定点観測ポイントが設けられます。
そこに配置されるのは、区の職員たち。
彼らが頼るのは、測定器でもAIでもなく、自分たちの目。
それがすべてです。
まず行うのは、「1平方メートルに何人いるか?」という密度の目測です。
混み合っていれば1㎡あたり4~5人、ゆったりしていれば2人程度。
その密度に観測範囲の面積を掛け合わせることで、1ポイントあたりの「おおよその人数」が割り出されます。
この測定は、夕方17時から夜の20時半までのあいだに、複数回繰り返されます。
人の流れは刻一刻と変わるため、一度の測定で終わりにはできないのです。
こうして各観測地点で導き出された人数を、墨田区・台東区・中央区の3つの区がそれぞれ合計し、最後にその数値をすべて足し合わせたものが、「来場者数」として公式に発表される数字になります。
喧騒のなか、静かに人を数え続ける人たちがいる。
93万人という数は、目立たぬ現場の仕事が丁寧に積み上げた結果なのです。
重複しても漏れても、それでも「だいたい」でいい
当然ながら、目測による人数カウントには正確さという点では限界があります。
同じ場所に座って長時間観覧していた人は、何度も測定されるうちに複数回カウントされるかもしれません。
逆に、建物の屋上や屋形船の上から見ていた人たちは、まるごとカウントされていない可能性もあります。
さらに、人の密度を見て「1平方メートルに3人くらい」と判断するのも、所詮は目分量。
観測者ごとにブレもありますし、夕暮れ時や混雑のなかでは、見落としも起きるでしょう。
それでも、なぜこの方法が受け入れられているのか──
答えは案外シンプルです。
これは「正確な人数」を知るための作業ではなく、「だいたいの規模感」を共有するための儀式だからです。
数字そのものよりも、前年との比較や報道における象徴性、そして「大勢の人が来たんだ」という実感を支える“物語の数字”として機能しているのです。
観客数は、イベントの熱量を数字に変換したもの。
その数字が多少ズレていても、人の熱気と雑踏の気配だけは、きっと間違いなく伝えているはずです。

最新のカウント術:ドローンか、スマホか、それとも…
AIやドローンの進化が話題になると、「ああ、もう人間が人間を数える時代じゃないな」と思わされます。
そして実際、街頭イベントの来場者数も、今やテクノロジーの力でかなり正確に推計できるようになっています。
たとえば、スマートフォンの位置情報をもとにした「人流データ」。
これを使えば、「どこに、どれくらいの人数が、どのくらい滞在したか」が、地図上でほぼリアルタイムに可視化されます。
もちろん、個人情報は伏せられたままですので、匿名性も守られています。
また、画像解析AIも進化しており、上空から撮影された写真や映像から、人の密度を自動的にカウントすることもできます。
ドローンで撮影し、AIで分析し、クラウドで集計。
── これで、ほぼ人間はいらなくなります。
数字だけを求めるならば、です。
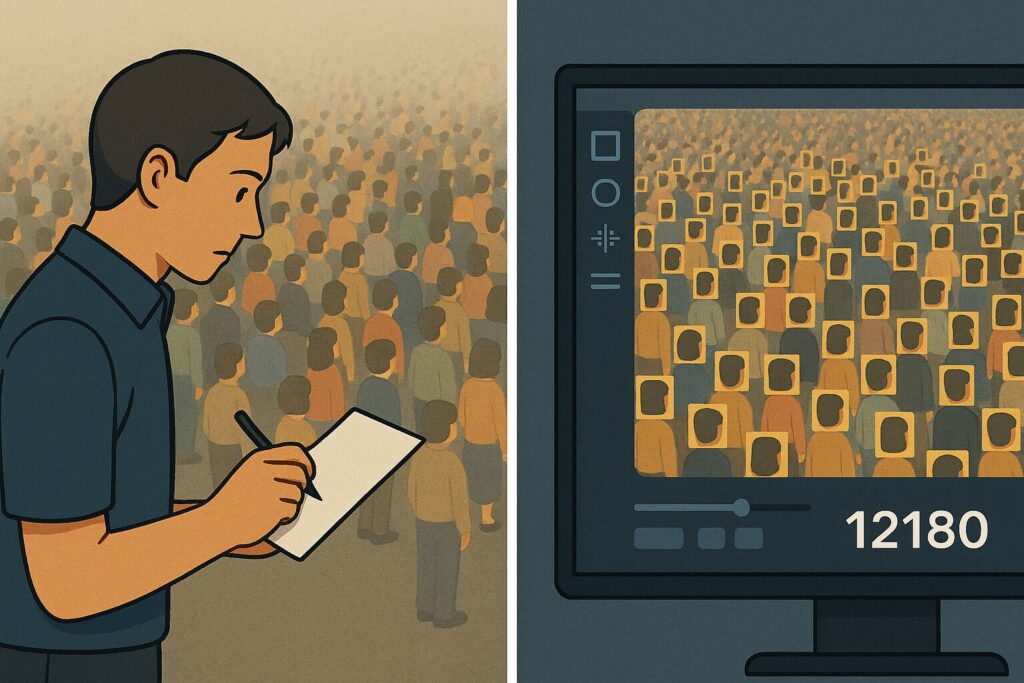
では、なぜ隅田川花火大会では、今もなお、人力カウントという、どこか懐かしい作業を、わざわざ続けているのでしょうか。
理由のひとつは、費用と運用の現実性です。
人手による目測にも、もちろんコストはかかります。
区の職員を大勢動員するわけですから、それなりの労力と準備が必要です。
それでも、特別な機器を導入せずに運用できるという点では、自治体にとっては取り組みやすい方法です。
加えて、同じ手法を毎年繰り返しているからこそ、過去との比較や傾向の把握がしやすいという利点もあります。
もうひとつの理由は、おそらく「これで十分」だからでしょう。
来場者数は、完璧な統計としてではなく、あくまで社会的な目安として発表されるものです。
100万人か93万人かの議論より、「たくさん来て大いににぎわった」が伝わることのほうが、大切なのかもしれません。
人が集まり、にぎわいが生まれ、その手応えを数字に変える。
その役目を果たすのであれば、カウントの方法は多少クラシックでも構わない──
そんな暗黙の了解が、今も現場には流れているようです。
「だいたい100万人」の先にあるもの
93万人か、それとも100万人か──
その違いにこだわる人は、そんなに多くはないでしょう。
それでも主催者が毎年、人の波を見つめ、数字をはじき出すのは、数字を割り出すこと自体に、意味があるからではないでしょうか。
正確ではない。
というより、そもそも正確な数字を知るなど最初から無理だと、私たちは薄々わかっています。
それでも、人が集まり、街が熱を帯びたあの時間を、「だいたいの数字」に置き換えることで、この一夜の出来事を記憶にとどめようとするのです。
「93万人」という数字は、たとえるなら──
「隅田川花火大会」というメインタイトルに添えられた、サブタイトルのようなもの。
その数字をきっかけに、誰かがまた、「あの年の花火はね」と語りはじめる。
そんな想い出の糸口のような役目を、この数字は果たしているのかもしれません。
参考文献・出典一覧
- Yahoo!ニュース編集部「「デモ」や「花火」の参加人数ってどう数えるの?」Yahoo!ニュース、2015年8月16日(2025年8月4日閲覧)
- 山二商事株式会社「昔ながらの人数の数え方」YAMANI公式サイト、2016年7月9日(2025年8月4日閲覧)
- 観光庁「観光入込客統計に関する共通基準(令和5年改訂版)」国土交通省 観光庁、2023年(2025年8月4日閲覧)









