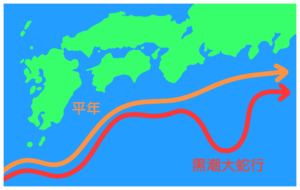病院は、白の王国だったはずだ
病院は、かつて「白の王国」でした。
しかし、いつからかその景色は変わりつつあります。
二十年前には異端とされた青や紺の「スクラブ」と呼ばれる衣装が、今では白衣と肩を並べる存在となっています。
白衣姿の医師たちも、気づけばカラフルな装いを選ぶようになり、ナースキャップはほとんど姿を消しました。
長い間、病院は白一色が醸し出す清潔さと威厳に包まれた空間でしたが、そこにさまざまな色が広がり、今では小さな虹が病院のあちこちに姿を見せているのです。
こうした変化を、単なる流行だと見なすのは早計です。
医療現場の色が変わってきた背景には、衛生面での事情や、患者への心理的配慮、そして社会の価値観の変化など、いくつもの要因が影響し合っているのです。
医療現場で「白」が定番になるまで
今から150年以上も前のことですが、当時の医師の正装は白ではなく黒でした。
19世紀半ばまで、ヨーロッパの医師たちは礼服の延長として黒いフロックコートをまとい、医療の現場にも神聖さと威厳を漂わせていたのです。
しかし、19世紀後半になると、衛生概念の進歩に伴い白衣が登場します。
白という色が持つ「清潔」や「純粋」というイメージが、病院に信頼と安心をもたらしました。
一方で、女性看護師の装いも大きく変わりました。
ナイチンゲールが率いた看護婦たちは、長袖のワンピースに袖なしの白いエプロン、そして帽子を身につけ、まさに“白衣の天使”の原型を作り上げました。
こうして医療の世界では、白が標準色として次第に定着していきます。

この流れは日本にも明治期に押し寄せました。
1885年、高木兼寛(たかき かねひろ)が創設した有志共立東京病院看護婦養成所では、ナイチンゲール看護学校を手本に、足元まで届く白の前掛けと帽子が導入されます。
そして、大正期になると白衣は全国に広まり、戦後の1950年代には保健衛生法や環境衛生法の制定をきっかけに、白衣の統一規格が定められました。
こうして病院に一歩足を踏み入れれば、「白」が医療の象徴であることは、誰の目にも明らかになっていったのです。
医療現場で「白」が好まれたわけ
なぜ、医療の現場では白が長く好まれてきたのでしょうか。
そこには「伝統だから」だけでは語り尽くせない、いくつもの合理的な背景があります。
まず、白は清潔感の象徴です。
その白さは、まるで嘘をつけない正直者のように、血液や体液の付着を隠さずさらけ出します。
一見「汚れが目立つ」という欠点は、医療の世界ではむしろ大きな利点です。
汚れにすぐ気づけば、即座に着替えや消毒ができるため、衛生管理がしやすいからです。
さらに、白は信頼と責任を象徴する色でもあります。
患者は白衣をまとった医療者に、自分の命を預ける覚悟で病院の門をくぐります。
その白は医師や看護師の専門性を際立たせ、「ここに来れば大丈夫だ」という安心感を患者に抱かせてきました。
白衣という布は、医療者と患者をつなぐ、目に見えない信頼の糸でもあるのです。
そして忘れてはならないのが、防護性です。
白衣は単なる衣装ではなく、薬品や体液が飛び散ったときに下の衣服を守る役割を果たしています。
コートのような形状は身体全体を覆う盾となり、内側の衣服に感染源が付着するのを防いでいるのです。
こうした理由を思えば、白が「医療の象徴」として長い間揺るぎない地位を保ってきたのも、ごく自然なことです。

「白一色」が「カラフル」に変わりつつある理由
「白一色」の不動のイメージに変化の兆しが見え始めたのは、ここ二十年ほどのことです。
まず、大きな理由のひとつが、患者への心理的影響です。
白衣は「清潔」の象徴である一方で、「冷たい」「権威的」「怖い」といった印象を与えることがあります。
白衣を目にするだけで血圧が上がる「白衣高血圧症」や、恐怖や不安を覚える「白衣症候群」という現象が生まれたのも、その表れでしょう。
その点、スクラブはモダンで親しみやすい印象を持ち、医師や看護師と患者との間に、より柔らかい空気を生み出します。
淡いパステルカラーやキャラクター柄、花柄やペールトーンといったデザインは、「思いやり」や「親しみ」の感情を呼び起こし、患者の不安を和らげる効果があります。
さらに、スクラブは衛生管理の面でも高く評価されています。
抗菌や防臭加工が施された素材が多く、高温での洗濯や消毒にも耐えられます。
白衣も、汚れが目立ちやすいという利点がありますが、スクラブは特に洗濯のしやすさという点で優れています。
また、白衣の袖口や裾はコートのように広がっているため、患者に触れやすく、汚染されやすいという弱点がありますが、スクラブはその点が異なります。
袖が短く、袖口も広がらないため、患者との接触を最小限に抑えることができ、機能面でも優れているのです。
加えて、男女兼用という点も大きな強みです。
1999年の男女雇用機会均等法の改正や、2002年の「看護師」への名称統一によって男性看護師が増えた背景もあり、スクラブは性別を問わず着用できるユニフォームとして、ますます医療現場に浸透していきました。

「白」から「カラフル」へ ── 色が語る医療の進化
医療現場が「白一色」から「カラフル」へと変わりつつある背景には、患者への心理的配慮、衛生や感染管理の合理性、そして職場の多様性への対応があります。
「10年前の常識が、今では非常識」と言われるほど、医療の世界は激しく姿を変えつつあります。
診断や治療だけでなく、医師や看護師の装いも、時代の流れに合わせて変化を求められているのです。
色彩の変化は、流行の変化ではありません。
そこには、医療現場で働く人々が、患者とのより良い関係や安全を追求し続けてきた努力が映し出されています。
次に病院を訪れたときには、白だけでなく、さまざまな色のユニフォームにも目を留めてみたいと思います。
その色こそが、医療が患者に寄り添おうとする、やさしい意思の灯りなのです。
参考文献・出典一覧
- 医師のともキャリア「白衣からスクラブへ | 医師の服装トレンドの変化とその理由」医師のともキャリア(2025年7月6日閲覧)
- イワサキユニフォーム「スクラブ・白衣・ケーシーの違いとは?医療ユニフォームの特徴やメリットについて種類別に徹底解説!」イワサキユニフォーム、2024年10月23日(2025年7月6日閲覧)
- ユニフォームタウン「医療用白衣はなぜ白い?歴史から読み取る白衣の謎と白い意味」ユニフォームタウン(2025年7月6日閲覧)
- RadiChubu「医療の現場で白衣を着る理由を尋ねてみたら、最近はそうでもないという話」RadiChubu、2018年10月11日(2025年7月6日閲覧)
- クラシコジャーナル「白衣・ナース服の歴史はいつから?現代のユニフォームの変化や医師・看護師の最新服装トレンドも解説」クラシコジャーナル、2021年8月11日(2025年7月6日閲覧)
- 大阪医科薬科大学「看護師白衣の変遷」大阪医科薬科大学、2019年1月17日(2025年7月6日閲覧)
- 庄山茂子、栃原裕、窪田恵子、青木久恵「異なるデザイン看護服に対する印象評価」『日本繊維製品消費科学会誌』第54巻第2号、日本繊維製品消費科学会、2013年
- 庄山茂子、栃原裕、窪田恵子、青木久恵「制服としての看護服の変遷と現代における看護服のデザインの違いが看護師および患者に与える心理的影響(2013年度報告)」文化学園大学リポジトリ(2025年7月6日閲覧)
- m3.com「医師の服装-開業医は白衣5割、勤務医はスクラブ5割」m3.com、2025年3月15日(2025年7月6日閲覧)
- 民間医局コネクト「勤務時の服装は、白衣派・スクラブ派が二強。お気に入りを着るとモチベーションアップにつながる傾向も 〜医師の身だしなみアンケート〜」民間医局コネクト、2024年9月20日(2025年7月6日閲覧)