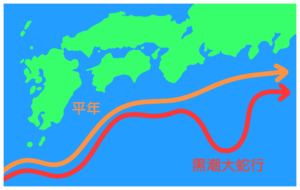「右か左か」、なぜ通行方向は分かれたのか
日本では、車は左側を走り、人は右側を歩くのが当たり前の光景です。
しかし世界に目を向けると、およそ7割の国では右側通行が主流となっています。
この違いは、単なる交通ルールの問題にとどまりません。
武器を扱う手の利き手、都市の構造、秩序をどう築いてきたかなど、文化や歴史の積み重ねが背景にあります。
通行方向の選択には、その社会が何を大切にしてきたかという価値観の痕跡が、静かに刻まれているのです。
剣を構える右手が決めた?
古代から中世のヨーロッパでは、多くの人が右利きでした。
そのため、正面から来る相手にすぐ応戦できるよう、右手で武器を抜きやすい左側を通るのが理にかなっていたと考えられています。
また、当時の人々は馬に左側から乗り降りしていました。
街道沿いの建物に近づきやすくする点でも、左側通行のほうが安全で合理的だったといえるでしょう。
ローマ時代の轍が語る「通行の実態」
この仮説を支える手がかりもあります。
1998年、イギリス・スウィンドン近郊で発見されたローマ時代の道です。
その道は採石場に通じており、左側の轍が浅く、右側の轍が深く削れていました。

荷車は空の状態で採石場へ向かい、重い石を積んで戻ってきたと考えられます。
つまり、軽い往路は左側を、重い復路は右側を通っていたのです。
これは、往復を通して左側通行に近い運用が行われていた可能性を示す発見です。
巡礼と秩序:教皇が決めた通行方向
1300年、ローマ教皇ボニファティウス8世は、聖年にローマを訪れる巡礼者に左側通行を求めたと伝えられています。
数十万人が一斉に集うなか、混雑を避け、秩序を保つための措置だったのでしょう。
通行方向に宿る、文化と思考の歴史
こうして見てくると、一見単純な通行方向にも、宗教的な秩序、身体の使い方、都市の構造など、さまざまな要素が関わっていたことが見えてきます。
「どちら側を通るか」という選択には、その社会が何を重んじ、どのように安全と秩序を築いてきたかという思考の痕跡が刻まれているのです。
革命と制度が通行方向を分けた
通行方向の違いが国家制度として明確に分かれるようになったのは、近世から近代にかけてのことです。
とくに大きな転機となったのが、フランス革命とナポレオンの登場でした。
フランス革命がもたらした右側通行
革命前のフランスでは、貴族が左側、庶民が右側を通るという暗黙の慣習がありました。
しかし、1789年のフランス革命によって、この身分的象徴は否定され、右側通行が市民社会の標準として広がっていきます。
その後、革命の流れを受けて登場したナポレオンは、右側通行を自らの支配地域にも導入しました。
この制度は、ベルギー、スペイン、ポーランド、イタリア北部など、征服した地域へと広がっていきます。
イギリスが守った左側通行
一方、ナポレオンの支配を受けなかったイギリスでは、伝統的な左側通行が守られました。
1835年に「ハイウェイ法(Highway Act)」が制定され、通行方向が法的に定められます。
この法制度は植民地にも伝わり、インド、オーストラリア、南アフリカなどでは、イギリス本国と同様に左側通行が根づいていきました。
アメリカでは運転の「習慣」が決めた
アメリカでは開拓時代から、荷馬車の御者が車両の左側に座り、右手でむちを振る慣習がありました。
この構造のため、右側通行の方がすれ違いに適していたと考えられます。
さらに20世紀初頭には、フォード社の「モデルT」が左ハンドルで大量に生産されるようになり、その影響で右側通行が制度として全米で定着していきました。
日本はなぜ「左」を選んだのか
日本が左側通行を採用したのは、明治期に導入されたイギリス式の鉄道技術の影響だと、しばしば語られます。
けれども、それより以前から、日本人の生活には「左側を通る」という感覚が根づいていたようです。
江戸時代に根づいていた左側通行の習慣
江戸時代、武士は刀を左腰に差していました。
すれ違うときに刀がぶつかるのを避けるため、互いに左側を歩くことが多かったとされます。
こうした身体感覚に根ざした行動様式は、町人のあいだにも広まりました。
街道や橋の上などでは、「左側通行」が自然に共有されていたと考えられます。

明治初期、鉄道に持ち込まれたイギリス式の左側通行
明治5年(1872年)、日本で最初の鉄道が新橋と横浜の間に開通します。
この鉄道はイギリス人技師の指導のもとに建設されました。
そのため、列車が左側のレールを走るイギリス式の通行方式がそのまま採用されました。
そして、鉄道の普及とともに、左側通行も一般の交通に広がっていきました。
慣習と技術、その両方が制度に結びついた
やがて、生活の慣習と鉄道の運用が、制度へとつながっていきます。
明治22年(1889年)には、人力車の営業に関する規則の中で、「車馬は左に避ける」と明記されました。
さらに1900年には、警視庁が東京で左側通行を正式に明文化します。
1920年には「道路取締令」によって全国的な統一が図られ、左側通行は日本の制度として確立されていきました。
このように、日常に根づいていた慣習と、導入された鉄道技術、そして行政の判断が重なり合った結果、日本では左側通行が制度化されたと考えられます。
「右か左か」に映る、社会のかたち
通行方向の違いは、単なる交通ルールの違いではありません。
その社会が何を「秩序」と考え、どのように制度を築いてきたか――つまり、社会のかたちそのものを映し出しています。
日本の左側通行もまた、外からの模倣ではなく、暮らしの中の慣習が制度へと形を変えていったものでした。
どちらの側を進むのか――その小さな選択の背後には、長い時間をかけて築かれた価値観や社会の輪郭がにじんでいます。
ふだん通る何気ない道に、そんな過去の思考の足跡が刻まれていると気づいたとき、私たちの世界は少しだけ立体的に見えてくるのかもしれません。
コラム:通行方向を変えた国々
通行方向を途中で変更した国はほとんどありません。しかし、実際にその大転換を実行した国もあります。
たとえば1967年、スウェーデンでは「Dagen H(Hデー)」と呼ばれる国家的改革が実施されました。この日を境に、同国は左側通行から右側通行へと一夜で切り替えたのです。
もちろん、ただのルール変更ではありません。交通標識や信号の向き、バス車両の構造に至るまで、大規模なインフラ整備が必要となりました。
その背景には、隣国との整合性を高める目的がありました。加えて、当時の車の9割が左ハンドルだったことも影響しています。右側通行にすることで、追い越し時の視認性を高め、交通安全の向上を図ったのです。
一方、2009年には南太平洋の島国サモアが、逆に右側通行から左側通行へと転換しました。この政策の主な理由は経済です。オーストラリアやニュージーランドからの左ハンドル中古車の輸入を促進しようという狙いがありました。とはいえ、国内では混乱や反対運動が起こり、社会には大きな揺れが生じました。
このように、一度定着した通行方向を変更するには、政治や経済だけではなく、国民生活全体を巻き込む覚悟が求められます。日々の暮らしに溶け込んでいる通行のルールには、その国が選び取ってきた価値観や歴史が、静かに刻まれているのです。
参考文献・出典一覧
- Peter Kincaid『The Rule of the Road: Why countries drive on the left or right』Greenwood Press、1986年
- エンゲルベルト・ケンペル(著)/斎藤信(訳)『江戸参府旅行日記』平凡社、1977年、P16
-
1835年「Highway Act」
legislation.gov.uk(2025年5月23日閲覧) -
The Economist
Why do most countries drive on the wrong side of the road?(2025年5月23日閲覧) -
WorldStandards.eu
Why do some countries drive on the left and others on the right?(2025年5月23日閲覧) -
NAPOLEON.ORG
Bullet Point #30 – Did Napoleon transform Paris?(2025年5月23日閲覧) -
National Geographic
The Right (and Left) Stuff: Why Countries Drive on Different Sides of the Road(2025年5月23日閲覧) -
JAF公式サイト
なぜ日本は左側通行なの?(2025年5月23日閲覧) -
Wikipedia
車両の通行側(2025年5月23日閲覧) -
BBC – Capital
A ‘thrilling’ mission to get the Swedish to change overnight(2025年5月23日閲覧) -
The Guardian
Samoa drivers switch sides of road in historic move(2025年5月23日閲覧)